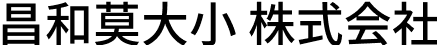どうも2025年10月に入社した新人未経験社員です。
中の人として靴下作りを見ている中で、
「もっと効率的にやればいいのに」そう思っていたことがあった。
僕たちは「少量多品種生産」という選択している。
いわゆる作る量は少ないけれど、色々な種類の靴下を作るということだ。
正直、同じ靴下を大量に、同じ設定でつくり続ければ、生産効率はぐっと高まる。
でも──僕たちがやっているのは、そんなやり方じゃない。
靴下づくりにも、生産スタイルがある
一口に“靴下工場”といっても、やり方はそれぞれだ。
たとえば「少量少品種」であれば、同じ機械設定で回し続けられるから、それなりに効率的。(まぁ少量少品種では経営が成り立たなくなることが多いが)
「大量少品種」であれば、さらに効率は上がり、スピードもコスト面も圧倒的に強い。
ユニクロやダイソーの靴下がこのスタイルに近い。
でも、僕たちが選んでいるのは「少量多品種」。
──正直、効率はめちゃくちゃ悪い。
なぜなら、機械の設定を頻繁に変えなければいけないからだ。
素材も、編み方も、丈も、締めつけ具合も、製品によって全く違う。
正直、非効率のかたまりだ。
でも、それでもやめようとは思わない。
むしろ、そこにこそ“モノづくりの楽しさ”があると思っている。
ランナーにも登山者にも──届けたいのは「ちょうどいい靴下」
なぜそんな手間をかけてまで、少量多品種にこだわるのか。
理由はシンプルだ。
「いろんな人に、ちゃんと合う靴下を届けたいから」。
たとえば、ランニング用ソックスひとつとっても──
・とにかくムレにくいものがほしい人
・耐久性を求める人
・グリップ力がないと困る人
・見た目がオシャレじゃないと履きたくない人
登山も同じだ。
・低山の日帰りハイクにちょうどいい靴下
・高山の縦走に耐えられる靴下
使う人も、使うシーンも違うなら、必要な靴下も違って当たり前だ。
だから、僕たちは細かく用途を分けて、それぞれに最適な一足を用意している。
「このソックスは、こういう人のためにある」と胸を張って言えるものを、つくりたいんだ。
量を売るより、「誰かのための一足」を
もちろん、大衆向けの靴下にも良さはある。
万人に合う設計、安価で手に入れやすい価格帯。
そういう靴下は、たくさんの人を支えている。
でも僕たちは、その道を選ばなかった。
万人には届かないかもしれないけれど、
「これを求めていた!」と感じてくれる人に、ちゃんと届く靴下をつくりたい。
一人ひとりの足元に寄り添って、「この人のために編んだ」と思えるような一足を届けたい。
実はこれが、靴下にこちらの感情だけではなく、お客様の感情も自然と乗ってくることに繋がる。
「とりあえずこの靴下を履いておけば安心」
「レースに出るときは絶対に履く」
そんなふうに“気持ちを預けられる存在”になっているのだ。
大袈裟と思っている方は、ぜひ当社の取扱いしているOLENOのオンラインショップのレビューを覗いてほしい。
僕たちは、靴下を編みながら──
そんなストーリーも一緒に紡いでいるのだ。
効率は悪くても、効き目のあるものを。
手間はかかっても、気持ちのこもったものを。
それが、僕たちが“少量多品種”という道を選んでいる理由だ。
そして──それでも、続けていきたい理由
なので、覚えることも多いし、機械の設定を変えたりするのは人間なので、ミスをする可能性もぐっと上がる。
でも──
それでも僕たちは、このやり方をやめないと思う。
なぜなら、そこに“つくり手の存在”がちゃんと残るからだ。
どんな靴下を、なぜつくるのか。誰のために、どんなシーンで使われるのか。
そのひとつひとつに意味があるということを、僕たちは忘れたくない。
たとえ効率が悪くても、完成までに何度もやり直しても、
最後に「この靴下、ほんまによかった」と言ってもらえたとき、
全部が報われたような気持ちになる。
きれいごとでもなく、自己満足でもなく──
「誰かの足元を本気で支える一本」を、今日もまた、機械の前で編んでいる。
そしてまたひとつ、僕たちの物語が紡がれていく。