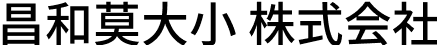「この靴下、いいですね」
展示会でも、オンラインショップでも、レビューでも、ありがたいことによくいただく言葉だ。
でも、それと同じくらい難しいのが──「いい靴下って、なんだろう?」という問い。
高ければ“いい靴下”?
機能が多ければ“いい靴下”?
ブランド名がついていれば“いい靴下”?
多分、どれも”正解”ではないと思う。
数字じゃ測れない”体感”の価値
たとえば、通気性や速乾性、グリップ性、フィット感。
確かにこれらは靴下のスペック(機能)として比較できる。でもそれがその人にとっての”いい”かどうかは、実際に履いてみないと分からない。
“いい靴下”って、意外とスペックや価値では決まらない。
それよりも「この靴下が、自分にとってどうだったか」──
その“体感”の積み重ねが、一番リアルな価値ではないかと思っている。
、、、、と思いたい。
「高い=いい」ではない。でも「安い=正義」でもない
誤解されることもあるけど、僕たちは「高い靴下が正しい」と思っているわけではない。
世の中には、安くても十分な品質の靴下はたくさんあるし、大量生産で支えられているライフスタイルもちゃんと存在する。
ただ──僕たちは、安さだけでは届けられない価値があることも知っている。
細かい部分にまで気を配って、肌に触れたときの質感や、洗濯を繰り返したときの強さ、
レースで走るときの信頼感や、旅先での安心感まで想像してつくる。
それをちゃんと届けるには、それなりのコストも、手間も、時間もかかる。
だからどうしても“安く”はできないけど、
そのぶん「ちゃんといい靴下を届けよう」という気持ちを、隅々まで込めている。
使い手と一緒に完成するモノづくり
“いい靴下”って、作って終わりじゃないと思う。
たとえば、「この靴下、もう3年履いてます」とか、
「夏は絶対この1足です」とか、そんな声をいただくたびに思う。
靴下が完成するのって、たぶん“履かれてから”なんだ。
工場で形になった瞬間じゃなくて、誰かが日常の中で使って、「これ、よかったな」って感じた瞬間。
つまり、“いいモノ”は、つくり手だけじゃつくれない。
使い手の体験と時間の経過があって、ようやく完成するんだと思う。
だからこそ、妥協せず、ちゃんと届けたい
「なんとなく良さそう」じゃなくて、「ちゃんといい」と思ってもらえるモノをつくるために、
靴下エンジニアは今日も、素材を選び、設定を調整し、試作を繰り返している。
時間はかかるし、効率は悪い。
でも、それでも。
「この靴下にしてよかった」
そんなふうに思ってもらえたときに、僕たちのモノづくりはようやく報われる。
“いいモノ”の定義は、人それぞれ違う。
でも、僕たちの中にある答えはずっと変わっていない。
「ちゃんと考えて、ちゃんと届ける」。それが、昌和莫大小(しょうわめりやす)の靴下エンジニアが思う“いいモノ”の最低条件だ。