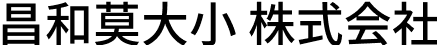僕たちは、「靴下をつくって売る会社」じゃないと思っている。
少なくとも、それだけでは足りないと思っている。
靴下という“モノ”を通じて、もっと深く、もっと対等に、誰かとつながっていたい。
そして、靴下を“共につくる”ことができたなら──
それが僕たちにとっての理想のモノづくりだし、これからの時代に求められる姿だと思う。
モノづくりは、届けてからが本番
工場で形になった瞬間に、靴下は完成するわけじゃない。
本当の意味で完成するのは、それを履いてくれる人の足元で、“体験”として成り立ったときだと思っている。
だからこそ、僕たちは「使い手」の存在を、ただの“お客さん”だとは思っていない。
履いて、感じて、伝えてくれる声が、次の靴下づくりの種になる。
つまり、モノづくりは僕たちだけのものじゃない。
履いてくれる人と一緒に育っていく、“共創”のプロセスだと思っている。
靴下がつなぐ、対等な関係
「この靴下、マラソンで自己ベスト出せました」
「冬山で使ってみたけど、まったくムレずに快適でした」
「このシリーズ、もうちょっと丈が短ければいいのに」
そんな声を聞くたびに、僕たちは気が引き締まる。
“評価される対象”としての靴下ではなく、“信頼される相棒”としての靴下を求められていることに気づかされるからだ。
靴下は、小さなプロダクトかもしれない。
でも、そこには必ず使う人の“意図”や“期待”がある。
その意図や期待に、ちゃんと向き合って応え続けること。それが、共創の第一歩だと思っている。
「好き」がつなぐ、開かれたモノづくり
僕たちの靴下は、万人受けするデザインじゃないかもしれない。
価格も決して安くないし、スペックの説明も少しマニアックだ。
でも、それでも「好き」と言ってくれる人がいる。
「履くと安心する」
「レースにはこれしか履けない」
「友達にも勧めました」
そう言ってくれる人たちがいる。
この“好き”は、ただの消費ではなく、共感の証だ。
そして、こういう“好き”を共有できる人たちと、靴下を一緒に育てていきたいと思っている。
共創には、手間も時間もかかるけれど
共創は、効率的な道ではない。
使い手の声をひとつずつ聞いて、試作して、改良して、また戻ってくる。
意見がぶつかることもあるし、思い通りにいかないこともある。
でも、それでも──その過程のなかに、確かに“つながり”が生まれる。
履く人と、編む人が、ただの“売り手と買い手”じゃなくなる瞬間。
それが僕たちにとっての、モノづくりの醍醐味だ。
これからも、「一緒につくる」を続けていきたい
僕たちは、誰でもいいとは思っていない。
でも、僕たちの靴下を“好き”だと言ってくれる人とは、長く、深くつながっていたい。
ただモノを届けるのではなく、想いを交わし、言葉を聞き、試行錯誤しながら一緒に歩んでいく。
そんな関係を、これからも大事にしたい。
靴下を編むという行為の先にあるのは──
「僕たちだけではつくれないモノを、誰かと一緒につくること」。
それこそが、僕たちの思う“モノづくりの本質”なのかもしれない。