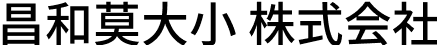2025年10月に入社して、約半年。
正直に言えば、それまで僕は「靴下って、ほどんと機械で勝手にできているもの」だと思っていた。
ボタンを押したら、自動販売機みたいに完成品がストンと出てくる。そんなイメージだった。
でも、現実はまるで違っていた。
1足の靴下が出来上がるまでに、これほど多くの人と工程が関わっているとは思っていなかったし、こんなにも“人の手”が必要だと思っていなかった。
■靴下は分業のかたまりだった
靴下を1足を仕上げるまでには、驚くほど多くの工程がある。
・糸の手配
・編立て(あみたて)←靴下クリエイターが担う
・つま先の縫製
・洗い、乾燥
・セット(形を整える)
・検品、包装
それぞれの工程を担うのは、全て別の工場や職人たちだ。
例えば、つま先の縫製は、履いた時にごろつきが出ないように、専用ミシンを使って縫い合わせる繊細な作業だ。表からは見えないが、足裏のフィーリングを左右する大事な工程である。
セットでは、アイロンのように高温の熱と圧を加えて形を整える。ここで商品としての”顔”が決まる。
最後に、専用の機械や経験豊富な職人による目視&手触りで異常がないかを確認し、1足ずつ丁寧に袋詰めされて出荷される。
ひとつひとつ工程が独立していて、それぞれの職人が専門性を持って関わっている。靴下はまさに「分業の塊だ」
■靴下工場といっても、大きな会社ではない
「工場」と聞くと、大規模なラインや社員が何十人もいるようなイメージを持つかもしれない。でも靴下産業においては、それとはちょっと違う。
関わってくれている工場の多くは、家族で運営されているいわゆる“家業”だ。
みんな、決して派手ではないが、何十年も同じ工程を担い、着実に技術を磨いてきた人たちだ。
もちろん、高齢化は進んでいるし、「もうしんどい」と漏らす声も聞く。
それでも辞めずに続けてくれているのは、金銭的な部分もあると思うが、そこには地元ならではの”繋がり”があるからだと思う。
代々受け継いできた仕事。長年取引をしてきた信頼関係。「自分がやめたら困る人がいる」という責任感。
効率や儲けだけでは測れない、人間らしい温度がそこにはあった。
■僕たちが価値を生まなければ、誰かにしわ寄せがいく
靴下は1社だけでは完結できる産業ではない。
だからこそ、僕たちのようにブランドを運営する立場が、“価値”をきちんとつけていかなければならないと思っている。
価格を下げれば売りやすくなるかもしれない。でもそのしわ寄せはきっと誰かに回ってしまう。
糸の質を落とす。工程を削る。検品チェックを甘くする。それはもう、僕たちが作りたい靴下ではなくなってしまう。
だから付加価値をつける。背景や想い、使っている糸の凄さ、工程の丁寧さ、履き心地。そういった「見えないけれど確かな違い」をちゃんと言葉にして伝えていく。
そして、作ってくれた人の想いがちゃんと報われるような仕組みを僕たちが作っていく。それが、広陵町という産地を未来につなげる、僕たちの役割だと思っている。
■最後に
1足の靴下の背景には、想像以上に多くの人が関わっている。
それを入社して初めて知った。
靴下はただの消耗品ではない、毎日履く、何気ないものだからこそ、そこに込められた仕事や技術が”当たり前”として受け入れられてしまっている。
でも、その裏にはたくさんの人の”手”があった。
僕たちはこらからも、その1足に関わる人がたちと共に、価値を守り、育て、伝えていきたいと思っている。
そして、今日もまた1足の靴下がこの町で生まれている。
それがきっと明日の誰かの足元を支える一足になると信じて、目の前のことを頑張っていきます。