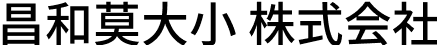靴下づくりの会社に入ってまだ間もないが、OEMという受託型のモノづくり、自社ブランドとしての発信、どちらも見る中で少しずつ見えてきたものがある。
それは、これからのモノづくりにとって本当に重要なのは「何を作るか」ではなく「誰が作るか」になっていくんじゃないか?ということだ。
■ 差別化できない時代に、“人”が際立つ
今の世の中、モノは溢れている。性能も、デザインも、価格も飽和状態だ。どのジャンルでも”そこそこいいもの”が簡単に手に入る。
そんな時代に「機能」で差別化するのはますます難しい。
では、何が選ばれる決め手になるのか?
僕は、”誰がつくったか”という背景や思想がこれからの価値になると思っている。
■ その会社が、そのブランドが、そしてその人が作るから意味がある
世の中には、全く同じスペックの商品でも、売れるものと売れないものがある。その差は何か?
たとえば、全く同じ設計・素材・価格の靴下があったとする。でも「誰が、どんな想いで、どんな技術で」それを作ったのかが見えると、価値の感じ方がまるで変わる。
そして、その”違い”は購入後にじわじわ効いてくる。「なんか安心する」「なんか好き」
この“なんか”を作っているのが、人間の感性であり、手間であり、物語(ストーリー)だ。端的に言うと、ブランド力と言うもの。
■職人=技術だけではなく、”思想を受け継ぐ人”
昔は「職人=技術の人」だった。手先が器用で、長年の経験を積み重ねたプロフェッショナル。
でもこれからは、それに加えて”思想を持つ人”が求められると思う。
・なぜその調整をするのか?
・なぜその工程をあえて残すか?
・どうしてそこまで丁寧にやるのか?
こうした問いに対して、「なんとなく」ではなく、自分の言葉で語れること。それが職人の役割になっていく気がしている。
技術は継承できる。でも、思想は共有しようとしなければ継承できない。
■モノづくりは「届けてこそ」意味がある
OEMとD2C、両方をやってきたからこそ感じるのは、当たり前だが「モノは届けてこそ初めて価値になる」ということだ。
いくら精度の高い靴下を編んでも、誰にも履かなければ意味がない。逆に、誰かに喜ばれた瞬間に、そこに価値が宿る。
この届けるという行為も、単なる販売ではなく、「とんだ想いで、どんな手で作られたか」を伝える営みだ。
だから今、靴下エンジニアには職人であると同時に、モノづくりのストーリーテラー(物語を語る人)でもあるべきなんじゃないかと思っている。
■ おわりに|これからの職人像
最後に、靴下に問わず、職人というのは「誰にも気づかれない”あと1%”を追いかけ続ける人」だと思います。そして、それを誰かに語れる人。
それは派手ではないし、見返りも少ないかもしれない。でも、その1%が「なんかいい」に必ずつながる。
その1%が、誰かの”当たり前”を支えている。
これからのモノづくりが、もっと人間らしく、もっと感情と結びつくものであってほしい。
僕自身、いっちょ前に語れる立場ではないけれど、この靴下エンジニアの道の先に、確かなものがあると信じてる。
そしてぜひ一人でも多くの方が、モノづくり、強いては靴下作りに興味を持っていただけることを楽しみにしている。モノづくりは思っているより素晴らしいし尊いものだ。
3部にわたって読んでくださった方がいたとしたら、本当にありがとうございました。