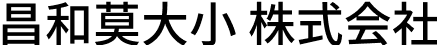「モノづくりの本質って、何だろう?」
前回の記事でも話した通り、自社ブランドとしてお客様に靴下を届ける中で、ありがたいことに日々たくさんの声が届くようになった。
「走りやすい」「下り坂で安心感がある」「これ以外履けなくなった」
それらの言葉を受け取るたびに、自分の中である疑問が膨らんでいった。
”なぜ靴下ひとつで、ここまで人の気持ちが動くのか?”
そしてそれは、”そもそもモノづくりってなんだろう”という問いに変わっていった。
■機能は飽和している時代
僕たちが作っている靴下は、いわゆる高機能ソックスと呼ばれるジャンルに入る。クッション性、吸湿性、耐久性、ホールド感、グリップ感。。。。
でも、こうしたスペックは今の時代ならある程度”揃えられて当たり前”だとも思う。ネットで検索すれば似たような商品が山ほど出てくる。
つまり、「便利」「性能」だけでは差別化できない。物価高の中、「価格」での差別化も限界がある。それでも僕たちの靴下が誰かの心に残るのは。そこに”何か”があるからだ。
■微調整という名の”感情”
靴下づくりの現場では、ミリ単位どころか糸1本の違いで履き心地が変わる。 季節によって湿度が変わり、糸の張り具合が微妙に変わる。 糸ロットや編み機の状態によっても微差が生まれる。
設計図どおりに編んでも「なぜか違う」ことがある。その違和感を逃さずに、言語化し、機械の設定を再調整していく作業。
これは良くも悪くも「人間の感覚」に依存している。AIは平均的に正しいものを生み出すのは得意だけど、”なんか違う”という違和感に気づけない。
この「違和感と向き合う力」こと、僕が感じている”人間にしかできないこと”の一つだ。古臭い言葉で言うと職人の仕事だ。
■ お客様の声に“正解”が宿っていた
繰り返しになるが、D2C(メーカーが直接顧客に商品を届ける)をやっていると、ときどき驚くようなレビューが届く。
「この靴下に出会って、ランニング人生が変わった」
「仕事の時も履くようになり、手放せません」
「もっと早くに出会っておけばよかった」
僕たちが当たり前と思っていたことが、誰かの”特別”になっていた。このとき、僕の中でストンと腑に落ちたことがあった。
「モノづくりの本質は、誰かの“当たり前”をつくること」
決して、派手である必要はない。むしろ、意識すらされないけど毎日選ばれてしまうもの。
そんな“無意識の信頼”を築けるモノをつくることが、 モノづくりの本質なんじゃないかと感じるようになった。
■ OEMの現場にも、ちゃんと“思想”はあった
僕たちの会社は長年、OEM(受託生産)をやってきた。それこそ「決められた仕様通りに納品する」ことが求められる世界だ。
でも、靴下エンジニアの人達の仕事を見ていると、ただの作業ではなかった。
「この素材なら、こっちの番手の方がいい」「この設計だと、着用時にズレるから一目落そう」
口に出さないけれど、すごく細かいこだわりが随所にあった。そこにあるのは、「誰が履くのかわからなくても、気持ちよくあってほしい」という建前ではなく、当たり前にまで落とし込んだ想いだった。
それって、”顔が見えない相手に対する、最大の誠実さ”だと思う。
■ 形のないものをつくる仕事
「誰でもできることを、誰よりも丁寧にやる。」「誰も気づかいないところを、誰よりも気にする。」そんな仕事が、靴下づくりにはたくさんある。
効率では測れないし、派手な成果も出ない。だけと、そういう”手間の積み重ね”こそが「この靴下じゃないダメなんです」という言葉に繋がっている気がする。
それは、”形のない価値を形にする”という、とでも人間らしい仕事だ。そしてきっとそれは、今後どれだけAIやテクノロジーが進化しても、残っていくものだと思う。
■ 次回へ
今回は、自分が思うモノづくりの本質について考えてみた。”やりがい”とか”誇り”とかそういった言葉に悩まされる人は多いと思うが、結局はどの仕事も誰かの役に立っている(詐欺とかは除く)時点でやりがいはあるし、誇りの持てる仕事に違いない。
なので、もう少し視点を変えて”人にしかできないこと“を”どのようにやっていく“かにこだわってみてもいいと思う。
・今までにないモノを生み出して、誰かの役に立つのか
・当たり前のことを丁寧にやり続けて、誰かの役に立つのか
・100→101を常に追求しつづけ、今よりもいいモノを作り、誰かの役に立つのか
これだけは言えるのは、モノづくりができる会社ではあれば、全てできるということだ。
次回は、さらに視野を広げて「これからのモノづくりはどう変わるのか?」「靴下エンジニアの役割はどうなるのか?」について、今の自分なりに考えてみたい。