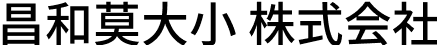奈良県広陵町の靴下工場に入社して約半年の30歳です。
自分も最初はそうだったが、ITやAI、VR、自動運転などそういった言葉とは無縁の業界に魅力を感じる人は少ないかもしれない。ただ、誇れることは全然ある。
「日本の靴下といえば奈良」
業界ではそう語られることがある。実際に奈良県は、全国の靴下生産量の約6割以上を占めており、日本一の産地である。
そして、その奈良の中でも特に生産が集中しているのが、僕たちの会社(昌和莫大小)がある「広陵町」だ。
人口は3万人ほどのこの小さな町に、数多くの靴下工場や関連企業が密集している。
言い換えれば——広陵町は日本の”足元”を支えてきた町だ。
■産業としての靴下
靴下は毎日履いて、毎日脱がれて、毎日洗濯される。消耗品であり、日用品であり、でも体の一部のように無意識に使われる存在。
そんな靴下を安定的に丁寧に何十年も作り続けてきた町がある。
それは一見、地味で注目されにくい産業かもしれない。でも、この「地味な産業の継続」こそ、地域を支え、日本の繊維業界を支えていることをもっと多くの人に知ってほしいと思っている。
■広陵町のものづくは特別
この町では、靴下を編むだけではなく
・編み立て
・縫製
・セットアップ
・検品・包装といった、靴下づくりのほぼ全ての工程を一貫して町内で完結させることができる。
つまり、町全体が工場のような機能を持っている。(最近は少しずつ少なくなってきているが)
そう聞くとすごく古臭そうな町と感じる人も多いと思うが、実際はそうでもない。
確かに、ハード面(工場や働いている人達)を見ると昭和感が漂うかもしれないが、密集している分情報の流れも早く、いまどきな靴下ブランドも数々登場している。
そして何より、若手の挑戦が許容されやすい雰囲気がある。だからこそ、新しいアイディアや技術も生まれやすく改善のスピードも早くなっている。
こうした独特な土壌が、広陵町を特別な靴下産地にしている。
■今や海外で作るのが当たり前の時代に
今、世の中に出回っている靴下の多くは海外で生産されている。中国やベトナム、インド、バングラデシュなど、より安く大量に作れる地域を目指して、多くの企業が生産を移してきた。
著名ブランドであっても「いかに安く作るか」に頭を悩ませ、コストの安い国を転々とすることも珍しくない。
もちろん、安く作ることが悪いわけではない。むしろ企業努力として普通に尊敬している。
コストを抑えながらも、ある程度の品質を維持する技術は、海外の工場にも全然ある。
でも、やっぱり「安いには安いなりの理由がある」。原材料、検品水準、製造スピード、工程の細やかさ。どこかで目に見えない”何か”を削っているケースも少なくない。
■海外からの視線
そんな時代だからこそ、最近では海外から「Made in Japan」の品質が再評価されつつある。特にヨーロッパやアジアの一部では、
・糸の選定から丁寧に作られている
・色々な部分に色々な機能を持たせる細かさ
・繊細なフィット感といった要素が、「メイド・イン・ジャパン」として静かに注目されている。
そこには、日本のモノづくりに対する圧倒的な”信頼“がある。いわゆる「日本人気質」とも言われる
・細部まで妥協しない姿勢
・当たり前のことを丁寧に積み上げる文化
・人に見えない部分こそ丁寧に、という美意識
これが”職人としての精巧さ”として伝わり、海外では一種のブランドとして認識されている。
それは世界中が”合理性”に振れ過ぎた反動として、「人の手の跡が残るもの」への信頼と魅力が戻ってきているからだと僕は思う。
■僕たち靴下エンジニアが背負っているもの
広陵町という地で靴下を作るということは、「全国1位の県の中で、中心地としてモノづくりを守り・伝える責任」を背負うことだ。
それはプレッシャーでもあるし、同時に大きな誇りでもある。
しかし、ただ靴下を作るだけではいけない。ただ靴下を作るだけなら、人の手はいらない。
100点を101点にしようとする気持ち、細かいズレや違和感に気づく美意識からくる感性、そして、それを一つの”想い”としてしっかり伝えていくこと——。
それら全てが、僕たちがこの町でモノづくりを続ける理由だ。
靴下という、誰にとっても”当たり前”な存在。だからこそ、それを丁寧に作ることには、“見えないけど、確かな価値がある”
見えないけれど、確かに”伝わる”。そんなモノづくりを、僕たちは信じて続けている。
■未来のために、目の前を積み重ねる
とはいえ、構える必要はない。大事なのは、今日の1足を、丁寧に妥協せずに「自分が作っているんだ」と思って作ること。
そして、それらをうまく伝えていくことができれば日本の靴下産業を守り、この産業を「未来につなげていく」ことはできるはずだ。うまく伝える人もちゃんといるので安心してほしい。
つくる、届ける、喜ばれる。
これからも、僕たちはこの町から“世界に届く靴下”を地道に、でも確かに作っていきたい。